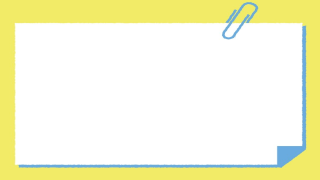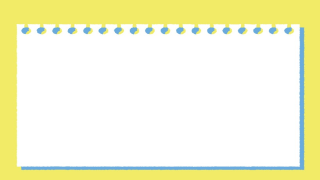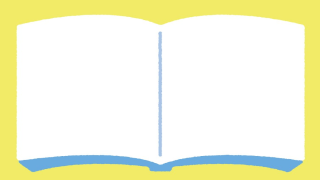科学するアート、キュレーションするサイエンスの面白さ
4月20日に新学部特別対談『科学するアート、キュレーションするサイエンスの面白さ』文京オープンキャンパスで開催。来年4月、文京キャンパスに本学初の理系学部「情報科学芸術学部」(設置認可申請中)を開設します。「情報科学」と「芸術」という、異なってみえる分野を合わせて学ぶことで、どんなことが身につき、社会で活躍できるようになるのか──。
最新の人気記事!
https://madatega.com/2934//
新学部就任の池上高志先生と長谷川祐子先生が高校生に語る特別対談を、4月20日(日)文京オープンキャンパスで開催します。高校生や保護者の方の疑問に応えながら、他大学にあまり例のない、この学問領域を学ぶワクワク感をお伝えします。
◆テーマ『科学するアート、キュレーションするサイエンスの面白さ』
・新学部長候補(現:東京大学大学院総合文化研究科教授)の池上高志氏
・前金沢21世紀美術館長でキュレーターの長谷川祐子氏
<対談概要>
新学部長に就任予定の池上高志先生は、AI(人工知能)を用いて自発的に動くようにしたプログラムをアンドロイド(人間型ロボット)に組み込み、オーケストラを指揮させたり、2体のアンドロイドによる対話劇を上演したり。こうした芸術表現を通して、科学技術と人間の共存や「生命とは何か」を一貫して追究する、複雑系科学と人工生命研究の第一人者です。
長谷川祐子先生は今春まで、国内屈指の来館者を誇る金沢21世紀美術館長で、美術館のプロデユースに関わられました。国内外での多くの国際展を通して、メディアアートや、科学とアートをつなぐ企画をしてきました。展覧会の企画立案や運営のプロフェショナルとして、新学部の教授に就任され、メディアアート史や情報のデザイン、キュレーションの理論と実践などを教えていただく予定です。
AIやアンドロイドを用いて科学とアートを探究する池上先生と、科学と深く関わる世界的アーティストたちのキュレーション(展覧会の企画・運営)を数多く手がけてきた長谷川先生は、まさに「情報科学芸術学部」の体現者。その二人だからこそ語れる、
▶これからの時代に必要となる学びとは
▶AIやアンドロイドと共存していく未来の「人としての生き方」とは
▶情報科学芸術学部を、どのような学びの場にしていきたいか
▶新学部に期待してほしいこと、志望してほしい生徒とは
<跡見学園女子大学が開設する「情報科学芸術学部」とは>
AI(人工知能)やデータサイエンス(情報科学)の進化は目覚ましく、私たちの社会や生活は急速に変化しています。新学部では、これからの社会に求められるAIやデータサイエンスの知識と技能を修得しながら、コンピューターを活用した芸術表現であるメディアアートを学びます。「科学」と「芸術」双方の分野を学ぶことで、多様な視点と新たな発想力を養い、未来を創造できる人材を育てたいと考えています。AIやロボットと共存する世界で、「人間だから」「私だから」できることをみつける4年間にします。
申込&詳細は同大学ウェブサイトにアクセス
https://www.atomi.ac.jp/univ/news/detail/15217/